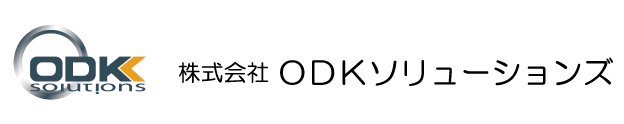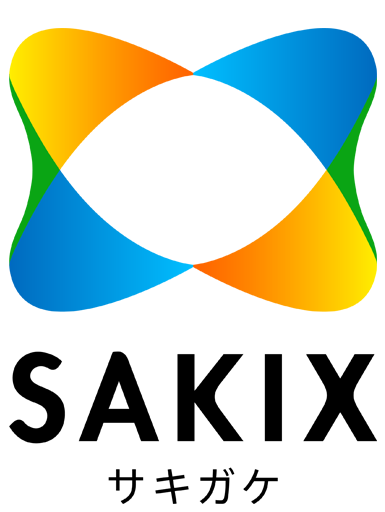コラム
備えあれば憂いなし -事業継続計画と巨大地震-

Ⅰ :Business Continuity Plan
金融システムの安定性と維持は、国力や国際競争力であるばかりでなく、公共財としての重要性が認識されております。
それ故に、市場関係者の間で、非常時対応の必要性が共有され、監督官庁も金融機関や市場に対し、いわゆる、BCP:Business Continuity Plan、事業継続計画の策定を指導しております。
それは、自然災害、事故、テロなどの緊急事態が発生した際に、事業への損害を最小限に抑えつつ、中核事業の継続や早期復旧を可能にし、従業員や顧客の安全を確保し、市場や企業への信頼を維持・向上させるための必須条件でしょう。
私は香港駐在中に、香港の監督機関や日本の金融庁のガイドラインを参考にしながら、BCPの策定とその演習に腐心したものです。
その主要な項目はこのようにまとめられます。
- 中核事業の特定と目標設定
優先して継続・復旧すべき事業を特定し、復旧目標時間を設定 - 代替策の準備
データセンターの中に事業継続できる程度の小規模なオフィスを設定する等、事業拠点や決済機能などの代替策を用意 - IT・データ対策
システムやデータのバックアップ、災害に強いデータセンターの利用、システムの二重化等を実行 - 従業員との連携
全従業員にBCPを周知徹底させ、実働部隊を二分割し、一方の部隊が稼働できなくとも、いま一方の部隊を動員できる体制を構築し演習を実施 - 顧客との連携
緊急時に提供できるサービスレベルについて、事前に顧客と協議
日本ではBCP策定に際し、最も想定される事態は地震ですが、香港では地震がほとんど無いこともあり*、台風や火災、9.11以降はテロ、といった事態を念頭に策定しました。
-
*厳密に言えば、香港で直下型地震が起きる可能性は極めて低い。ただし、年に数回は台湾や中国内陸部などでの地震のゆれが届いて、ほとんど体感できないような地震は発生している。
Ⅱ :思いがけない発動
香港現地法人でBCPが発令されたのは、21世紀の感染症として猛威を振るった、重症急性呼吸器症候群:SARS、通称サーズが契機となりました。
2002年11月に広東省で発生した重症急性呼吸器症候群:SARSは、翌年2月に感染地の広州市から親族の祝宴にかけつけた医師により香港にもたらされたとされる。同医師の宿泊したホテルから感染者が続発し、そのうちの1人が入院したプリンス・オブ・ウェールズ病院で、医療関係者、入院患者、見舞客など100名以上の集団感染が発生した。さらに、その外来透析患者の1人が高層団地群の淘大花園(アモイガーデンズ)アパートE棟を訪れたことから、団地全体で感染者321名、死者42名の惨劇となった。6月23日に世界保健機構(WHO)が感染地から除外するまで、香港では1,755名が罹患し299名が死亡した。感染が終息するまでに、計4カ月を要した。
【JETRO、地域分析・レポート『(中国・潮流)SARSを踏まえた香港の新型コロナウイルス対策』より】思いがけない事態でBCPが発動され、また、内外の人的往来が遮断され、孤立無援といったところでの業務継続は、なかなかスリリングな体験でした。
欧米の金融機関では、サーズの流行以前に中国南部で謎の病気が蔓延しているとの情報から、いち早く家族を本国に返す措置をとりましたが、日系の金融機関はワンテンポ遅れていた記憶があります。
欧米の金融機関が独自にWHOとの情報パイプを持っていたのか、あるいはアジアでの医療体制に不信を抱いていたのか、真相は不明です。
遅ればせながら、家族を日本に返した日系企業の駐在員が、香港の繁華街で羽を伸ばす姿は、いささか悲哀に満ちたものでした。
Ⅲ :阪神・淡路大震災と東日本大震災
さて、私は阪神・淡路大震災と東日本大震災という、日本を揺るがした未曽有の大地震を、香港駐在中に目撃することになりました。
無論、発生直後には出張中の従業員の安全確認、駐在員の家族の安否確認に集中しておりました。
阪神・淡路大震災の折にはインターネット前夜の時代で、オフィスのQUICK端末を叩くたびに犠牲者の数が増えていく様子に慄然といたしました。
若い金融人諸氏には、何のことか理解できないもしれませんが、株価やニュースのリアルタイム確認にはQUICK社の卓上端末が主流だった時代、その画面は自動更新されず、いちいちキーを叩いてアップデートする必要があったものです。
東日本大震災では、それとは全く異なった光景が展開されました。
BBC やNHKの衛星放送、さらにはネット映像は、地震で発生した津波に人や車がのみ込まれるさまが同時中継されるという凄惨なものでした。
そんな状況の中、週明けには東京本社在勤であるはずの外国人スタッフが多数、香港に避難してくるという事態に現場は混乱します。
それは本社におけるプロダクト毎のBCPがありながら、香港現地のBCPと事前すり合わせが充分でなかったことが混乱に拍車を掛けた原因でしょう。
Ⅳ :巨大地震と金融市場
さて、政府の発表している地震の長期予測*では、南海トラフ地震や首都直下地震の発生がかなり高い確率で予想されており、日本海溝や千島海溝で地震が発生した場合の影響などが報告されております。
*地震調査研究推進本部の紹介
平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の経験を活かし地震に関する調査研究の成果を社会に伝え、政府として一元的に推進するために設置された特別の機関です。
日本の地震予知研究の第一人者、長尾年恭 東海大学客員教授によると、関東大震災、阪神・淡路大震災、東日本大震災、能登半島地震が、近代日本における巨大地震と目されているようです。
長尾 年恭(ながお としやす)
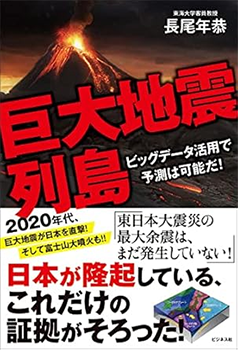
- 1955年生まれ
- 東京大学大学院理学系研究科修了・理学博士
- 静岡県立大学および東海大学客員教授
- 地震・火山に関する電磁現象国際WG委員長
- 一般社団法人「日本地震予知学会」会長
- 認定NPO法人「富士山測候所を活用する会」理事
- 東海大学海洋研究所教授時代に、地震予知研究センター長、海洋研究所長、地球環境科学研究科長等を歴任
- 専門は固体地球物理学。
- 地震予知研究を通じた減災や、富士山噴火予知をライフワークとし、大学院在学中に第22次日本南極地域観測隊に参加、昭和基地で越冬した経験を持つ
兜町の古老の記録では、1923年9月1日(土)に発生した関東大震災は、このように記憶されております。
東京株式取引所の建物も全焼し、兜町一帯が焼野原となった中、10月27日から焼け跡の天幕内で株式の現物取引を開始しました。その後、株式市場は回復し、兜町はすっかり近代的な街並みに生まれ変わりました。
開設140周年より】
東京株式市場は一時閉鎖、震災直後の混乱で株価は急落したが、復興特需により数年で持ち直した様子です。
時代は、東京市場が国際的な投資家を呼び込むどころか、単なるローカル市場に過ぎないものでしたので、市場の閉鎖が国際金融市場に影響を与えることはありませんでした。
それでは、それ以降の巨大地震の影響はどのようなものでしょうか?
Ⅰ.1995年1月17日(火)阪神・淡路大震災
- 発生直後
1月17日の早朝に発生。当日の日経平均は前日比90円安の1万9,241円で引けた。その後、被害の大きさが明らかになるにつれ、翌営業日以降も、小幅ながらも下げ幅を拡大。そして1週間後の1月23日には、前日比1,055円安という5%超の下落率を記録し、1万7,785円で引けた。 - 市場心理
神戸・阪神地域は港湾機能に代表される物流拠点であり、その麻痺が懸念された。復興需要期待で建設株が上昇、保険株や鉄道株などは売られた。 - その後
被害額は10兆円規模とされ、日本全体のGDP比でみれば限定的だったが、株価の持ち直しに年内一杯かかった。
Ⅱ.2011年3月11日(金) 東日本大震災
- 発生直後
東日本大震災は3月11日の午後2時46分に発生。場中だったこともあり、発生直後から売り注文が続いた。当日の終値は前日比179円安の1万254円だった。
その後、福島原発事故の状況も明らかになり、翌営業日以降も売りは続いた。3月14日には633円安の9,620円、そして15日には1,015円安の暴落となる8,605円。1987年のブラック・マンデー、2008年のリーマン・ショックに次ぐ、過去3番目となる下落率(10.55%)を記録した。
- 市場心理
特に原子力事故による長期リスク、サプライチェーンの寸断、電力不足懸念が強く意識され、輸出関連株、電力株、自動車株などが売られた。 - その後
日銀の大量流動性供給、復興需要への期待もあったが、株価の本格的な回復には時間が掛かった。
Ⅲ.2024年1月1日(月) 能登半島地震
- 発生直後
正月休場中で取引はなかったが、4日大発会で日経平均株価は3日続落し、前営業日比175円88銭(0.53%)安の3万3,288円29銭で終えた。能登半島地震の経済への影響を警戒した売りも出て、日経平均の下げ幅は午前に770円に達する場面があった。 - 市場心理
能登半島地域は人口や経済規模が限定的で、全国的な供給網やインフラに直結する影響は小さいとみられた。 - その後
政府の迅速な復旧支援、観光・建設関連への復興需要期待が一部銘柄の押し上げ要因となったが、株価全体への影響は軽微。
この三つのケースをまとめると、大地震発生後の市場には次のような傾向がうかがえます。
- 短期的なショック安
大地震発生直後は不安心理と経済活動停滞懸念から株価は下落。特に原発事故など「全国的リスク」が伴う場合は下落幅が大きい。
損害保険会社は巨額の保険金支払いが予想され、銀行も融資不安から影響を受けるため、金融・保険株や、鉄道、電力、建設など直接打撃を受けるインフラ関連株が一時的に売られる。 - 復興需要による持ち直し
建設、資材、住宅関連株が上昇し、市場全体も政策対応を背景に数週間〜数か月で回復する。
ただ、被災地の生産停止やサプライチェーンの寸断は、マクロ経済と企業収益に影響を及ぼし、特に輸出産業である自動車・電子部品な銘柄の株価の重しになる。
また、東日本大震災後、原発停止に伴い、エネルギー政策や規制の変化から、電力株が下落し、代替エネルギー関連が上昇した場面もありました。 - 影響度の差
被災地の規模と全国への波及度によって市場へのインパクトは大きく異なる。
結論は、「大地震=短期的にはショック安+長期的には復興期待で回復」という傾向のようです。
ただし、東日本大震災のように原子力事故など複合的なシステミックリスクが重なると、下落規模も回復までの不確実性も、格段に大きくなります。
Ⅴ :備えはできていますか?
もののちからに
ひかれゆく
わがあしあとの
おぼつかなしや
さて、この歌は、関東大震災の震災復興事業に奔走した京都生まれの女流歌人、九条武子のもので、この句を刻んだ歌碑が東京、築地本願寺の境内にあります。

本願寺派布教使の田坂亜紀子氏によると、本句は自分を奮い立たせしっかりと生きているようでも、自らの力ではどうにもならない出来事を目の当たりにした時に、そうはできない自分を思い知らされることがある、と解かれております。
確実にやってくる大地震への心の備え、できていますか?
<参考>
- 金融庁
- 香港金融管理局:Hong Kong Monetary Authority
- JETRO
- 日本取引所グループ
- 日本経済新聞
- 地震調査研究推進本部
- 巨大地震列島/東海大学客員教授 長尾年恭(著)
- 震災から1ヵ月の日本株式相場を振り返る
2011年4月フイデリティ証券 - マネーフロートレポート59
震災後、海外投資家は日本株を買い増し
2011年4月三菱UFJリサーチ&コンサルティング - 中央区観光協会
[ 2025.10.31 ]
[執筆者プロフィール]
一燈。1980年大手証券会社入社。企業派遣留学として米国でMBA取得。その後、シンガポール・香港駐在を通じアジアビジネスに、 また本社経営企画部門で経営戦略の立案等に関わる。