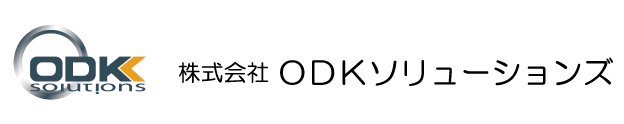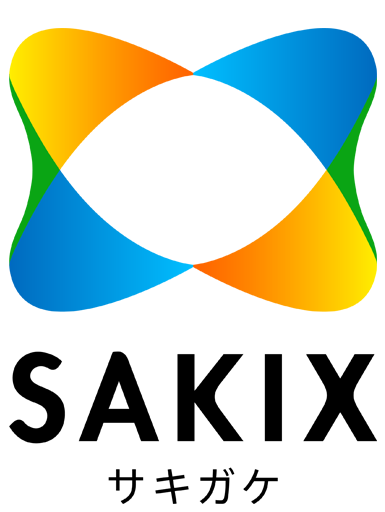コラム
手数料無料化への道のり

1987年(昭和62年)9月、野村証券は連結ベースで5,409億円の経常利益を上げ、トヨタ自動車をおさえて日本一の高収益企業となりました。(注:当時の証券会社の多くが9月決算を採用しておりました。)
野村證券百年史には1987年9月期の収益動向、特に株式関連業務については次のように記されております。
株式流通市場は、公定歩合の引下げや景気の回復等を背景に、国内機関投資家の投資が活発となった。1987年2月には日本電信電話(NTT)株式が東証に上場され、4月には東証第一部の時価総額がニューヨーク証券取引所(NYSE)の時価総額を抜く場面も見られた。日経平均株価も1987年9月には過去最高値となる2万6,118円を記録した。こうした株式運用のニーズが一段と高まる中で、当社は株式投資情報提供体制の充実やトレーディング体制の一層の整備に努めて、対応を図った。その結果、株式委託手数料収入は前期を大きく上回った。
当時は私も東京勤務であったため、テレビ番組で野村証券の営業現場にカメラが入ったり、研修中の新入社員に密着したりする番組を目撃してその注目度を肌で感じておりました。 NTTブームやバブル経済の狂騒といった背景もあり、証券各社は軒並み高収益を記録、並み居る製造業を凌駕して我が世の春を謳歌しておりましたが、出る杭は打たれるとばかりに、儲け過ぎ批判も広く展開されることとなりました。
では、なぜこの時期の証券会社は歴史的な高収益を上げることが出来たのでしょうか? その理由の一端に、当時の証券会社は大蔵大臣による免許制で、株式委託手数料も細かく規定された、1%程度の固定制であったことがあげられます。 証券業界内部でさえ、生活物資を扱う商社が証券会社並みの手数料を徴収したら社会問題になるのでは?との声までありました。 一方、海外の市場をみると、米国では1975年にニューヨーク証券取引所の株式手数料が(実施が5月1日だったためメーデーと呼ばれます。)、英国でも1986年には手数料自由化(ビッグバン)が断行されておりました。 そのため、日本でも株式委託手数料の自由化があるべき将来像として意識されており、実務的な議論も業界と監督官庁である大蔵省の間で始まっておりました。 しかしながら、日経平均株価が1989年(平成元年)12月29日の大納会に最高値38,915円87銭をつけたのをピークとして、市場は暴落に転じ、湾岸危機、原油価格高騰、公定歩合の急激な引き上げなどにより、1990年(平成2年)10月1日には一時20,000円割れと、9か月あまりの間に半値近い水準にまで暴落し、証券界は長い、長い冬の時代に入ります。 そんな不安の中で、主たる収益源のブローカー収入に大きな影響が出る手数料自由化は、証券界にとり死活問題でしたが、公正取引委員会を中心にカルテルではないかとの批判もあり、次第に株式委託手数料の自由化致し方なしとされて行きます。 ただ、自由化は避けられないものの、悪化する一方の経営環境もあり、「可能な限りゆっくりと」というのが証券界の本音であり、結果として「段階的な株式委託手数料の自由化」という道を進むことになります。 その結果、1994年(平成6年)4月には1銘柄の売買代金が10億円を超える部分につき、ついで98年4月には売買代金5,000万円超の取引につき株式委託手数料の自由化が断行されます。 1996年(平成8年)6月14日付で東証正会員協会から発表された「株式委託手数料自由化問題について」 という報告には業界の苦悩が滲み出ております。
- 証券会社経営に与える影響
(1)証券会社の収益に与える影響
証券会社は大幅な収益減となり、特に小規模会社に大きな影響が生じるものと予想され、多くの証券会社が経営困難に陥る恐れがある。
(2)業務展開に与える影響
多様な業務への展開を早急に探らなければならないが、多くの証券会社が不利な競争を強いられ、証券市場の寡占化が進む恐れがある。 - 投資家に与える影響
(1)機関投資家に与える影響
機関投資家は日本株の海外取引を増加させる可能性もある。
(2) 個人投資家に与える影響
個人投資家にフルサービスを行う場合は、相応の手数料引上げを行わざるを得ない。
この報告では、上記のような、おっかなびっくりの業界の懸念に加え、ディーリング等の多様な業務の規制緩和、有価証券取引税の即時撤廃等の要望を併記しておりました。
最終的に、橋本龍太郎内閣が提唱した金融制度改革(日本版ビッグバン)により、銀行・証券・保険間の相互参入の促進、投資信託の銀行窓口販売の解禁、株式売買手数料の自由化、取引所集中義務の撤廃、持ち株会社制度の導入、連結決算制度の本格導入などが98年12月1日施行の金融システム改革法によって実施され、ここに全面的な株式委託手数料の引下げ競争が開始されたのです。 ちょうどその時機に、対面や電話での取引が主流であった証券営業の世界に、インターネットという通信革命によって、人件費や間接費の大幅削減も可能な新しい株式販売経路として、オンライン証券が出現し、一気に普及することになります。 手数料を低く抑えることにより口座獲得を狙い、ある程度の口座獲得が出来たら、さらに手数料を引き下げる、この循環がビジネス・モデルとして成立するならば、その究極の形態は「手数料セロ」のビジネスでしょう。 米国では2013年設立のロビンフッド・マーケッツが手数料無料の株式売買サービスを開始して、ミレニアル世代(18~36歳)中心に顧客を集めておりました。 さらに、オンライン証券大手チャールズ・シュワブが2019年10月インターネットを通じた株式、上場投資信託(ETF)、オプションの売買委託手数料を撤廃、同業他社も追随したことにより、米国は一気にゼロ手数料時代に突入しました。 その競争に耐えきれなかったTDアメリトレードはチャールズ・シュワブに、Eトレードはモルガン・スタンレーに、各々買収され大きな業界再編成が進行しました。
日本でも米国のケースのように、ネット経由の注文に課す手数料をゼロと想定しても、信用取引の融資金利や証券の品貸料で収益を上げられるという議論もありましたが、そのためには、やはり厚い顧客基盤は必要であり、競争は熾烈を極めるであろうと予想出来ました。 2023年、SBI証券が満を持して、さらに楽天証券が追従して10月からの手数料完全無料化を宣言し、この分野での競争に火蓋が切られました。 そのきっかけとなりましたのは、岸田政権の掲げる資産所得倍増プランと、国民に提供されたNISA/新NISAという投資家優遇プランでしょう。 かつてのマル優とは異なり、最初に選んだ金融機関が固定化しがちなNISAでは、どんなことをしてでも顧客の囲い込みを図るという経営戦略は合理的なものです。 SBI証券は総合金融機関として多様な金融ビジネスの積み上げ、楽天証券は楽天経済圏の構築という目標はいささか異なるものの、目の前の顧客争奪戦はオンライン証券の業界再編の始まりでもあります。 マネックス証券はNTTドコモの子会社として、auカブドットコム証券は大株主のKDDIと連携して、大手でも大和証券が若年層をターゲットに大和コネクト証券を設立して、各々スマホ経由の注文を獲得しようとしており、この動きも日本型の業界再編といっても過言ではないでしょう。 また、SBI証券や楽天証券にしても、連携を深める地方銀行や独立系の金融アドヴァイザーを使い、対面営業にも商機を見出し、提供する金融サービスの多様化を図ろうとしております。
一方、投資家の立場に立ってみると、投資判断に資する情報提供や投資機会の助言が豊富で、投資収益に見合う手数料であるならば合理的であるとの考え方や、人間関係、取引の利便性も考慮して、現在でも一部の中堅証券ではそれなりの手数料を徴収しております。 しかしながら、岸田政権の掲げる資産所得倍増を目指す機運の中では、なかなかに困難な道ではないでしょうか?
特に「長期的な資産形成」への早道が手数料というコストの削減と、利益や配当に対する節税とするならば、一時的な市場情報よりも、そこに至るプロセスへの助言が求められるのではないでしょうか? また、大手証券が指向する富裕層ビジネスも、やはり一時的な市場情報ではなく、資産保全や、事業承継の助言が求められ、手数料ビジネスとは異なるものが求められるのではないでしょうか?
多様化する金融ビジネスの中で、ブローカー業務自体の収益比率が著しく低減する可能性もあります。 さらには、長く証券会社の収入基盤であったブローカー業務自体の存続も問われる時代となり、オーバーブローカー論どころか、ブローカー専業証券の不要論も出て来るかもしれません。
[参考文献]
野村證券百年史
実録 バブル金融史/恩田饒(著)河出書房新社
[2023.11 ]
[執筆者プロフィール]
一燈。1980年大手証券会社入社。企業派遣留学として米国でMBA取得。その後、シンガポール・香港駐在を通じアジアビジネスに、 また本社経営企画部門で経営戦略の立案等に関わる。