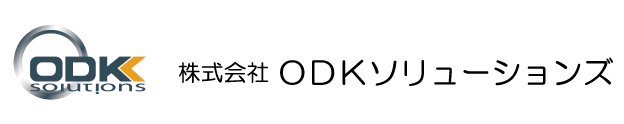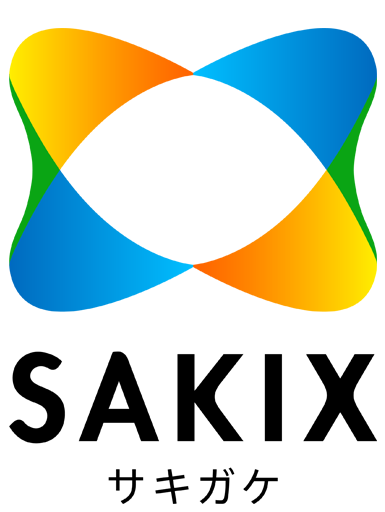コラム
アノマリーってなんだ?
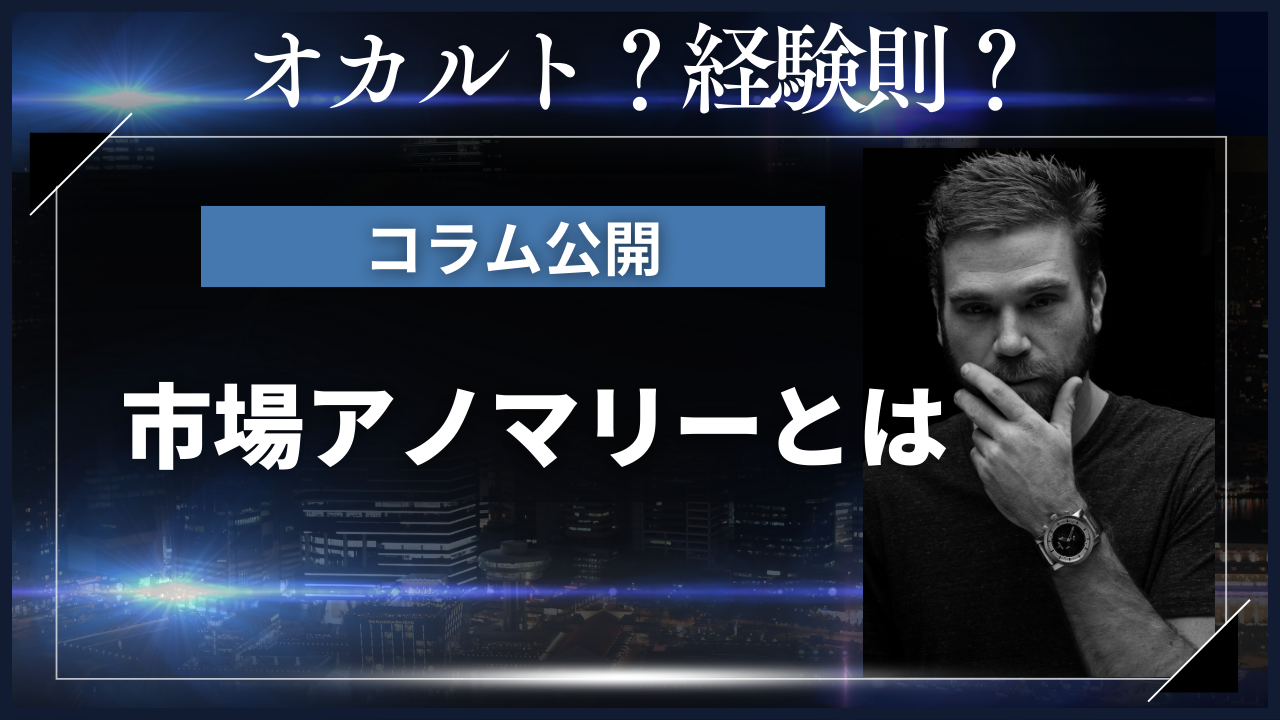
序 :「年頭ご挨拶」から
日本取引所グループCEO、山道 裕己氏は、2025年の「年頭ご挨拶」の一節で次のように述べられました。
干支は巳です。相場の格言では「辰巳天井」と言われていますが、ヘビは脱皮を繰り返しながら変化成長を遂げます。今年は、昨年からまた一皮剝けて成長したマーケットとなることを期待したいと思います。
私は御屠蘇気分のまま目にした山道CEOの挨拶に、相場格言の意味するところはひとまず置きながら、手堅い年頭所感にまとめた話術に、妙に感心してしまいました。
それはさておき、このように市場関係者は、様々な発言の機会に相場格言を引用します。
その多くが落語の“まくら”のように、あるいは俳句の季語のように、時世時節(ときよじせつ)に寄り添うことでもありますが、なによりも関係者にとって、骨身に染みている共通体験であるからかもしれません。
一方、報道や雑誌を通じて、市場関係者以外の方々も、相場格言やアノマリーに触れる機会が増えております。
NISAを活用する個人投資家の中にも、投資のタイミングや投資商品について、そんな事柄を気にする方もいらっしゃり、いささか驚くばかりです。
そんな時代に、いま一度、アノマリーについて考えてみましょう。
Ⅰ.アノマリーとは?
SMBC日興証券のサイト内に『初めてでもわかりやすい用語集』という証券用語の説明セクションがあります。
その一角に懇切丁寧に説明されておりますので、まず、これを出発点としてみましょう。
【アノマリー】- アノマリー(Anomaly)とは、 現代ポートフォリオ理論や相場に関する理論の枠組みでは説明することができないものの、経験的に観測できるマーケットの規則性のこと です。
- アノマリーの代表的なものとして、「小型株効果」、「低PER効果」、「配当利回り効果」、「1月効果」などがあります。
- たとえば小型株効果とは、小型株で構成されたポートフォリオは、市場平均よりも相対的にリターンが高いという事象のことですが、現代ポートフォリオ理論の代表的なモデル(CAPM)では、市場が効率的であれば証券価格は大型株、小型株にかかわらず、そのリスクによって決まると結論付けています。したがって、小型株だけ相対的にリターンが高いというのは、現代ポートフォリオ理論では説明しきれない事象なのです。
- アノマリー(Anomaly)は「変異性」と訳されることが多いのですが、文字通り、説明しきれない「変な」「異質な」事象といえます。
- このアノマリー等をうまく利用して、市場平均を上回る運用成果を目指す運用手法はアクティブ運用のひとつです。
(注:下線は筆者による)
まさしく非科学的な経験則ですが、投資の最前線では、それを前提とした戦略を構築して成果を上げようとする投資家も多数いらっしゃるので、完全に否定すべきものでもありません。
マーケットの大勢についていくならば「勝ち馬に乗れ」、逆張りに徹するならば「人の行く裏に桜あり花の山」と、これまた相場格言に行きつくのも御愛嬌ですが、近年では行動科学、あるいは行動経済学という学問の領域でアノマリーを説明しようという動きも活発です。
Ⅱ.アノマリーの検証
それでは、この経験則をより精緻な統計学を駆使して検証して、その経験則をより高い次元で止揚しようとする研究はあるのでしょうか?
日本では日経平均に代表される指数を対象とした研究はみられるものの、個別銘柄が絡む事象の研究はあまりありません。
それは第二次世界大戦により取引所取引が統合され、戦後は取引自体が中止となっていた期間がある事とも無縁ではありません。
即ち、戦時中は1943年(昭和18年)に日本証券取引所1カ所に統合・縮小され、敗戦後の1945年(昭和20年)には取引所自体の閉鎖から1949年(昭和24年)5月16日の取引再開まで、日本の株式市場には長いブラックアウトの時期が存在しました。
このような非連続性は株価検証の障害になっているのではないでしょうか?
もうひとつは 株価データそのもの です。
国立国会図書館のリサーチナビに「株価の調べ方」と入力すると、罫線雑誌を中心にいくつか挙げられておりますが、体系的な資料は見当たりません。
なにより紙に記載された記録では、長期の統計値を算出するには、データ入力だけでも気の遠くなるような労力が必要です。
誰でも気軽に、かつ安価にアクセスできるようなデータベースの不在が、日本における投資研究の大きな障害となっているのではないでしょうか?
ノーベル経済学賞におけるこの分野での受賞者を見ると圧倒的にアメリカの学者が多いのも、コンピュータ技術の発展に加えて、この手のデータベースの存在が大きな理由でしょう。
その代表格にシカゴ大学が整備する、証券価格研究センターCenter for Research in Security Prices(CRSP)があります。
CRSPが提供するデータは、35か国の大手金融機関、政府機関、一流大学の研究機関など、600 を超える加入者に信頼されており、そのデータは次のような方々をサポートしています。
- アカデミックな研究者・・・・研究成果が厳密な分析に耐え、正確性を保つ必要がある研究者
- 定量分析アナリスト・・・・投資モデルの策定と検証を行うアナリスト
- 政策立案者及び規制当局・・・・金融や経済研究の基礎として完全なデータを必要とする政府機関
CRSP のデータベースに保存されている主要なデータには次のようものが含まれます。
- NYSEの普通株(1926年以降)
- AMEXの普通株(1962年以降)
- NASDAQの普通株(1972年以降)
- CRSP インデックス
- ナスダックとS&P 500総合指数
- NASDAQおよびAMEX業界指数
- 米国債
驚くことに、ニューヨーク証券取引所(NYSE)の上場銘柄については100年近いデータが保持されており、歴史的な暴騰・暴落についても検証対象にすることが可能なのです。
このように米国では、統計学的検証に耐えるだけの長期データが提供されており、アノマリーの様な経験則の実証研究も盛んです。
Ⅲ.アノマリーの世界
ここで再度申し上げますが、アノマリーに理論的な根拠はありません。
しかしながら、多くの投資家がそれを共有するようになると、その経験則を使えば、市場を上回る成果を獲得できる可能もあります。
合理的な説明ができない
≠
投資行動の参考にならない
また、景気循環や市場サイクルから、一定の周期性が存在するとすれば、そこにアノマリーを信じて投資する投資家も存在するでしょう。
季節・時期のアノマリー
また、個別の投資資産でも、その属性から独自の動きが経験則として蓄積され、アノマリーが形成されます。
投資対象の属性に関するアノマリー
さらに、現在ではPCの発展から、幾つかの事象との相関関係を検証する回帰分析が手軽にできるようになりました。 私が学んだビジネススクールで学生間のジョークに“One Regression, Two Regression…”、「一に回帰分析、二に回帰分析。。。」というものがありました。 経営管理のあらゆる場面で統計分析!という教義を嘆く自虐的な冗談ですが、投資の世界では意外な事象と投資に相関関係が発見され、話題を呼ぶこともあります。
意外なアノマリー
このような範疇において、いくつかの代表的アノマリーを見ていきましょう。
季節・時期のアノマリー- 1月効果
マーケットにおいて1月の収益率が、他の月よりも高くなりやすい現象のことですが、年末に税金対策としての売りが出て新年1月にその反動が来るとか、年が明けると新たな資金流入がしやすくなる等々が原因といわれています。 - 節分天井、彼岸底
多くの国内企業で第3四半期決算が行われる2月上旬に株価が高値になる現象で、節分天井以降、3月中旬のお彼岸の時期まで株価は下がる傾向があるとの言です。
彼岸の時期を過ぎると4月以降の新年度の株高を期待した資金が回ってくるため、3月中旬が底値になりやすいといわれており、これを「彼岸底」呼ぶわけです。 - 夏枯れ相場
7月から8月にかけて、市場が閑散期となり、株価軟調になりやすいアノマリーのことで、とりわけ8月になると多くの投資家や市場関係者が夏期休暇を取得するのが要因といわれています。
私は兜町のベテラン証券マンから、株式関係者の関心が高校野球に向くからという解説を伺ったことがあります。 - 掉尾の一振(年末ラリー)
文字どおり年末にかけて株価が上昇するというアノマリーで、年末に一儲けして新年を迎えたい願望から、相場や一部の銘柄が活況になることです。 - 月替わり効果
機関投資家のリバランスが月末に行われる、給料日が月の後半に多いなどが要因として月の変わり目に株価が上昇しやすいアノマリーのことです。 - 二日新甫は荒れる
証券業界では月の最初の取引日を「新甫(しんぽ)」と呼びます。しかしながら1日が休日の場合、最初の取引日は2日になるとになります。こんなとき相場は大きく変動しやすい傾向にあると云われ、このアノマリーが生まれました。
ただ、私はカレンダーの日柄から来る三日新甫ですとか四日新甫という言い方は聞いたことがありません。 - 十二支のアノマリー
辰巳(タツミ)天井、午(ウマ)尻下がり、未(ヒツジ)辛抱、申酉(サルトリ)騒ぎ、戌(イヌ)笑い、亥(イ)固まる。子(ネ)は繁盛、丑(ウシ)つまずき、寅(トラ)千里を走り、卯(ウサギ)跳ねる
年や巳年は株価が天井をつけ、午年は下がる傾向。未年で辛抱したのちに、申年・酉年は値動きが激しくなる。戌年は笑いたくなるほどの良い相場。その後亥年は落ち着いた動き。子年は上昇相場になりやすいが、丑年でつまずき、寅年は寅が勢いよく走り抜けるため相場が荒れるが、卯年で相場は跳ね上昇する。
- 小型株効果
時価総額が小さく流動性の低い銘柄は、大型株に比べて機関投資家の需給が入りにくく、個人投資家による投機対象になりやすいものです。 - 割安株効果
割安株ほどリターンが高く、割高株ほどリターンが低くなる現象のことですが、割安を図る指標はPBRやPER等の指標ですので既にファンダメンタル分析でしょう。 - 配当アノマリー
権利付き最終売買日に向け、高配当株の株価が市場を上回ります。一部の投資家による売り買いセットでの配当取りテクニックも背景にあり、意外と確度が高いかもしれません。 - モメンタム効果/リターン・リバーサル効果
相場が一方向に進みやすく、上昇している銘柄はさらに上昇し、値下がりしている銘柄はさらに下落するモメンタム効果、逆に値上がり後に値下がりする、あるいは値下がり後に値上がりする相場のアノマリーです。
- サザエさん効果
毎週日曜日の夕刻に放送されるテレビアニメ「サザエさん」にちなんだアノマリーです。
2005年、大和総研から発表されたリポートは、証券業界だけにとどまらず、景気回復期にあった日本の至る所で引用されるほど、大きな話題となりました。
『サザエさん』の視聴率が上がると東証株価指数が下がり、逆に『サザエさん』の視聴率が下がると上昇するという経験則で、その相関係数は0.86という高い数値を示しており、ニューヨーク株式市場の株価指数と東証株価指数の相関係数0.56に比べても高いという驚きの報告でした。
これには個人消費の影響があると推論され、高視聴率は景気が悪くて消費者が自宅にいるため消費に悪影響を与えている、と分析されておりました。
大和総研は翌2006年に、サザエさんに続いてドリームズ・カム・トゥルーの人気と株価指数が比例するというリポートも発表して二匹目のドジョウを狙いましたが、こちらは繰り返し言及されることはありませんでした。
単に当時の男社会の証券界で、ドリームズ・カム・トゥルーの知名度が低かっただけかもしれません。
Ⅳ.まとめ
日本の相場の起源は江戸時代の米先物にさかのぼることができると云われます。
江戸時代、諸藩が年貢として集めた米の多くは、大坂をはじめとする大都市へと運ばれました。諸藩は、中之島周辺の蔵屋敷に納めた年貢米を入札制によって米仲買人に売却し、落札者には米切手という1枚当たり10石の米との交換を約束した証券を発行しました。この米切手には、未着米や将来の収穫米も含まれ、これらが盛んに売買されるようになったと云われます。
享保15年(1730年)、江戸幕府は堂島で行われる正米商い(しょうまいあきない・米切手を売買する現物市場)と帳合米商い(ちょうあいまいあきない・米の代表取引銘柄を帳面上で売買する先物市場)を公認し、堂島米市場と呼ばれる公的市場を成立させます。
近代取引所に通じる会員制度、清算機能などが整えられた堂島米市場は、わが国における取引所の起源とされるとともに、 世界における組織的な先物取引所の先駆け として広く知られています。
ここで培われた取引制度や慣行の多くは、明治以降の商品・証券・金融先物取引所に受け継がれました。
近代に入り、渋沢栄一らが「東京株式取引所」を、五代友厚らが「大阪株式取引所」を創設、第一次世界大戦や関東大震災、さらには第二次世界大戦前後の混乱といった影響を受けるものの、現在に至る市場の発展は歴史的遺産といっても過言ではありません。
日本において市場アノマリーとは、証券市場のみならず、江戸時代の米市場の取引にまで遡ることのできる貴重な体験なのです。
それは非科学的な体験譚ながら、時には投資家に味方してくれるもので、まさしく「儲ける」とは信ずる者なのです。
<参考>
- 日本取引所グループ
- Center for Research in Security Prices(CRSP)
- SMBC日興証券、野村證券、大和証券
- 日本経済新聞
[ 2025.02.28 ]
[執筆者プロフィール]
一燈。1980年大手証券会社入社。企業派遣留学として米国でMBA取得。その後、シンガポール・香港駐在を通じアジアビジネスに、 また本社経営企画部門で経営戦略の立案等に関わる。