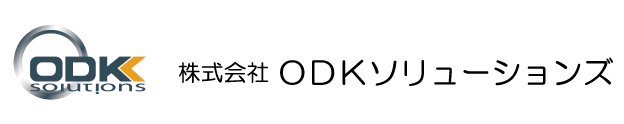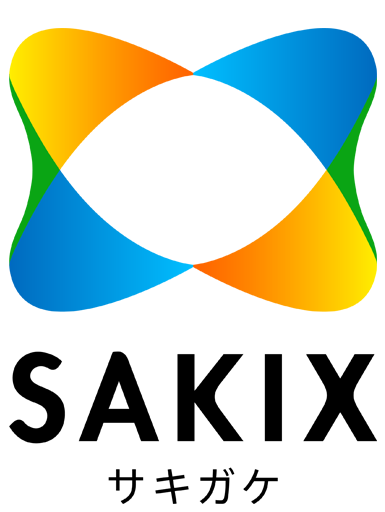コラム
金融資本市場探訪:映画や文学での描かれ方

序 :人は何故、興味を抱くのか?
金融資本市場を舞台にする映画や小説には多々ありますが、何故、人々の興味を惹きつけるのでしょうか?
それは、単なる「金儲け」や「株価の上げ下げ」以上に、社会構造や人間性の本質に迫ることができる格好の題材だからではないでしょうか。
もうすこし、突っ込んで考えてみましょう。
1.欲望・野心・恐怖・・・人間の心理を描きやすい
金融資本市場は「欲望の集積地」であり、登場人物たちの野望、強欲、嫉妬、恐れが極限まで引き出され、人々の心に大きな印象を残します。
2.ドラマ性が高く、興奮と緊張感を演出しやすい
暴騰・暴落といった市場の動きから、インサイダー取引・粉飾決算などの犯罪行為まで、スキャンダルやサスペンスに溢れ、物語を盛り上げる事件に満ちております。
3.現代社会の構造や矛盾を浮き彫りにできる
金融資本市場は、資本主義そのものの象徴であり、時代の格差・腐敗や政府や規制当局の限界といった課題をタイムリーに、かつ象徴的に扱えることができます。
4.リアリズムとフィクションの融合が可能
実際の大きな経済事件、例えば山一證券の自主廃業、ライブドア事件、リーマン・ショック等々を題材にしながら、創作の人物を絡めたりして、リアリティと物語性を両立できます。
5.「金銭:Money」という普遍的なテーマを扱える
金銭:Moneyはどんな人間にも影響を与えるため、登場人物の決断や葛藤が、普遍的なテーマとして提示されます。
6.知的興味と専門性を刺激できる
作家自身が金融資本市場に関心を持っていたり、業界の出身者だったりすることも多く、複雑な仕組みを解き明かす快感を作品に盛り込めることができます。
要は金融資本市場を舞台にすることで、極限状態の人間模様を描き、同時に現代社会の制度や価値観を批評できる、これがこの分野が人気の理由でしょう。
それでは具体的にどのような題材に分類されるのでしょうか?
Ⅰ.掲げられているテーマは?
いろいろな切り口から分類してみましょう。
1.舞台別の分類
- 株式市場・証券取引
主人公がトレーダー、ブローカー、アナリストなどの業界人 - 金融犯罪・スキャンダル
インサイダー取引、粉飾決算、詐欺事件 - 金融危機・経済破綻
バブル崩壊、リーマン・ショック、通貨危機、経営陣のモラルハザード - 中央銀行・マクロ経済政策
金利政策、為替介入、財政金融政策 - 金融業界の人間ドラマ
セールス、インベストメント・バンカー、ファンド・マネージャー、アナリスト、バックオフィス等の苦悩や成長
2.登場人物の立場別分類
- 金融のプロ側
証券マン、ファンド・マネージャー - 投資家・一般市民側
個人投資家 - 規制・監督側
政府、中央銀行、監督官庁 - 犯罪者側
詐欺師、インサイダー
3.時代背景別
- 1980年代バブル期
日本や米国の金融自由化期 - 1990年代金融危機
アジア通貨危機・日本の不良債権問題 - 2008年リーマン・ショック
世界的な金融システム不安 - 近未来・仮想通貨時代
未知な領域への挑戦
4.地域別
- 日本市場
- 米国市場
- 欧州の金融市場(ロンドン・フランクフルト)
- アジア新興市場(香港・上海・シンガポール)
5.フィクション vs ノンフィクション
- フィクション:小説・ドラマ形式
- ノンフィクション:実話ベース、ドキュメンタリー
これらを踏まえて、具体的にどのような作品が挙げられるのでしょうか?
私見ですが、欧州の作品は登場人物の人物描写に偏り金融市場が背景で希薄になりがちで、また、アジア新興国の作品は日本では入手困難な作品も多いという事情がありますので、ここは、世界最大の金融資本市場を持つ米国と、我が国、この二つの地域に絞って考えてみましょう。
Ⅱ.映像作品では?
1. 米国編
なんといっても一番に挙げたい作品は1987年公開のアメリカ映画『ウォール街:Wall Street』でしょう。
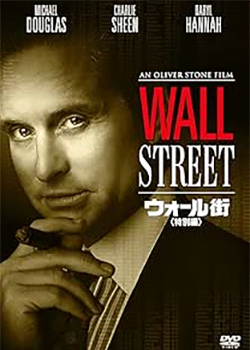
主人公の若手証券マンが、大口顧客と結託してインサイダー取引に手を染め、転落していくさまを描いて世界中で大ヒットした作品です。
なかでも、本作でアカデミー主演男優賞を獲得したマイケル・ダグラス扮する、投資家ゴードン・ゲッコーが放つ「Greed is good!強欲は善だ!」という台詞は、今でも頻繁に引用されるほど強烈なものでした。
本作は米国の投資家アイヴァン・ボウスキーと投資銀行ドレクセル・バーナム・ランベールをめぐるインサイダー取引をモデルとしているとされております。私は全盛期のアイヴァン・ボウスキーのスピーチを目撃したことがありますが、その一挙一動はマイケル・ダグラスの演技が表象するような傲岸不遜なものでした。
本作は、前章でまとめた多くの題材を取り入れながら、分かり易い作品に仕上げたところに成功の要因がありそうです。
ニューヨーク市場を舞台とした近年の作品には次のようなものもあります。
『マネー・ショート 華麗なる大逆転:The Big Short』2015年
リーマン・ショック直前、サブプライム危機を見抜いた投資家たちの実話を基にした作品です。
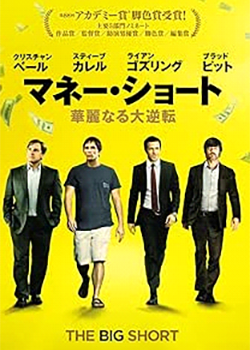
『マージン・コール:Margin Call』2011年
金融危機前夜の投資銀行を舞台にした24時間の緊迫ドラマです。
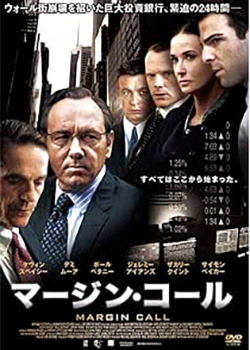
ちょっと毛色が異なりますが、私の記憶に残る作品に『大逆転:Trading Places』1983年という米国のコメディ映画があります。
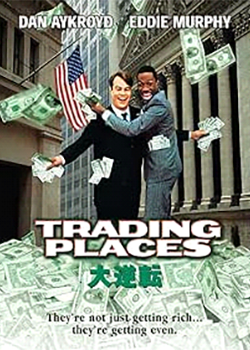
本作のクライマックスは、先物取引所におけるオレンジジュース先物の取引で、いわゆるオープン・アウトクライ:Open Outcry方式の取引が再現されているのです。
ピット(pit)と呼ばれる場所にトレーダーが集合し、互いに叫び合って注文を成立させる、即ち、トレーダーが特定の価格で売買したいという意思を大声でピット内で表明し、その価格で売買に応じるトレーダーが合意すると売買契約が成立します。
伝統的集団相対取引と云ったところですが、電子取引の普及により、時代遅れのような取引方式とされつつありますが、IT革命以前のChicago Mercantile Exchange:CMEやSingapore International Monetary Exchange:SIMEXでのオープン・アウトクライ取引は大変な活気が満ちていたものです。
本作でも、まだまだ市場参加者による直接取引が主力だった時代を追体験することができます。
2. 日本編
『ハゲタカ』2009年

外資系ファンドと企業再生をめぐる戦いを描いた重厚な経済ドラマですが、M&Aや企業買収を主軸に、株式市場の変動やTOB(株式公開買い付け)といった現場が差し込まれます。
『金融腐蝕列島〔呪縛〕』1999年
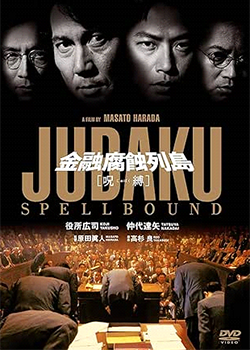
第一勧業銀行の総会屋利益供与事件をベースにした作品で、株式市場や企業の株主対応も描かれます。
『半沢直樹』シリーズ(2013年・2020年、ドラマTBS)
バブル後の銀行業界を中心に、証券取引、敵対的買収、株価操作をテーマに取り入れた人気ドラマです。
『しんがり〜山一證券 最後の聖戦〜』(2015年、ドラマWOWOW)

不正会計や“飛ばし”と呼ばれる不適切取引により大手証券の一角であった山一證券の崩壊と、その後日譚が描かれます。
Ⅲ.文学作品では?
1. 米国編
ザ・ウルフ・オブ・ウォールストリート:The Wolf of Wall Street/ジョーダン・ベルフォート:Jordan Belfort(著)
ニューヨークのウォール街で株式ブローカーとして急成長し、派手な生活と不正取引に溺れた著者自身の自伝的小説で、金融詐欺、薬物依存、無軌道な豪遊が赤裸々に描かれます。2013年にはマーティン・スコセッシ監督、レオナルド・ディカプリオ主演で映画化されております。
ライアーズ・ポーカー:Liar’s Poker/マイケル・ルイス:Michael Lewis(著)
1980年代のウォール街の投資銀行ソロモン・ブラザーズの内部を描いたノンフィクションに近い小説と云われ、投資銀行の裏側、トレーダーたちの駆け引き、金融バブルの様子が描写されます。
ザ・ビッグ・ショート:The Big Short/マイケル・ルイス:Michael Lewis(著)
2008年のリーマン・ショック前夜、住宅ローン担保証券の崩壊を見抜いた少数の投資家たちの実話で、株式市場の危機や金融商品の複雑性をドラマチックに描いております。映画編でご紹介した作品の原作でもあります。
2. 日本編
日本では企業や金融情勢を継続してテーマに取り上げる作家も多数いらっしゃいます。
その中では、その業界で経験を積まれた後に作家活動に入られた方も多く、いきおい内容はリアリティに富んだものになります。
- 獅子 文六 大番
- 清水 一行 小説兜町
- 高杉 良 小説巨大証券、金融腐蝕列島シリーズ
- 幸田 真音 日本国債
- 江上 剛 非情銀行、銀行総務特命
- 池井戸 潤 半沢直樹シリーズ
- 真山 仁 ハゲタカ
- 橘 玲 マネーロンダリング
- 黒木 亮 トップレフト
- 清武英利 山一證券最後の12人
金融の世界を描いた作品ではありませんが、その作品のなかに、意外な場面を発見する場合もあります。
『楡家の人びと』や『どくとるマンボウ航海記』で知られる北杜夫は、壮年期に発症した双極性障害から、株売買に入れ上げ、巨額の損失を蒙りました。そのありさまは著者自身によるエッセイや、ご家族の回想記により知ることが出来ます。
『ふらんす物語』や『濹東綺譚』で知られる永井荷風は、父親の遺産で、その高等遊民的暮らしを支えておりましたが、彼は遺産を銀行預金だけでなく、株式でも運用しており、日記文学の最高峰と呼ばれる『断腸亭日乗』の中でも、しばしば証券会社を訪れ、運用指示を与える記述がみられます。
このお二人の対照的な投資行動に、個人投資家のあり方について考えるきっかけにもすることができます。
追:思いだすことは?
『鬼平犯科帳』や『剣客商売』で知られる池波正太郎は中学を卒業してから旧軍に入隊するまで、兜町(シマ)の証券会社で、古き良き時代の株式取引の現場を経験します。その頃の体験は『青春忘れもの』や『食卓の情景』といった随筆集に収められております。
むかしの証券界の片隅で、丁稚奉公からの兜町の暮らし、そんな日々の中で株券の「書き換え」や先輩に言いつけられた雑用に町を奔り回る池波少年。
私がこの世界に足を踏み入れた1980年代には、既に株主の権利管理(発生、移転及び消滅)は、証券保管振替機構や証券会社など電子的に行う方向に突き進んでいたため、「書き換え」という作業自体、なじみが薄いモノになりつつありました。
後年、アジアの新興市場で、現地株のブローカー業務を立ち上げた折、集中決済システムの未整備から、まさしく、この「書き換え」の手順を構築したもので、現地事務所の一角に、株券の裏面に会社印を押す/株券を配送する専門スタッフを雇用しておりました。
その現地のスタッフに、戦前の兜町で走り回る池波少年を見た思いがしたものです。
おんりい・いえすたでい!
[ 2025.07.30 ]
[執筆者プロフィール]
一燈。1980年大手証券会社入社。企業派遣留学として米国でMBA取得。その後、シンガポール・香港駐在を通じアジアビジネスに、 また本社経営企画部門で経営戦略の立案等に関わる。